Table of Contents
夏野菜の代表格、ピーマン!実は、家庭菜園でも比較的簡単に育てられる野菜なんです。nippongardening.comでは、ピーマン 育てに興味がある初心者の方に向けて、種まきから収穫までのポイントを分かりやすく解説します。美味しいピーマンを育てるためのコツや、トラブル対策もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
項目 | ポイント |
|---|---|
種まき・育苗 | 発芽適温(25~30℃)を保つ、本葉2枚でポットに移植 |
畑の準備・定植 | 水はけの良い土、ナス科野菜の連作は避ける、株間は50cm前後 |
仕立て方 | 1番花の下から出た側枝を2本残し、3本仕立てにする |
追肥 | 定植2~3週間後から2~3週間おきに化成肥料を追肥 |
病害虫対策 | アブラムシ、ヨトウムシ、タバコガ、ウイルス病に注意 |
収穫 | 最初の収穫やたくさん実がついたときは若採りして株の負担を軽くする |
初心者必見! 驚くほど簡単なピーマン 育て
1. ピーマン 育て: 種まきから苗作り
ピーマンの種まき: 適した時期と方法
ピーマンの種まきは、4月~5月頃が適しています。暖かい地域では3月下旬からでもOKです。種をまくときは、育苗ポットやセルトレイに培養土を入れ、1か所に2~3粒ずつ種をまきます。種まき後は、土を軽くかぶせて水をたっぷりあげましょう。発芽するまでは、土が乾かないように注意して水やりを続けましょう。ピーマンは寒さに弱いので、発芽するまでは室内の日当たりの良い場所で管理するのがおすすめです。発芽適温は25~30℃なので、保温シートやビニール袋をかぶせてあげると発芽しやすくなります。
ピーマンの苗作り: ポット上げと管理
種をまいてから1~2週間ほどで発芽します。双葉が開いたら、元気な苗を1本だけ残して間引きします。本葉が2~3枚になったら、9cmポットに植え替えます。この作業を「ポット上げ」といいます。ポット上げ後は、日当たりの良い場所で育て、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをします。また、2週間に1回程度、液体肥料を与えて栄養補給をしましょう。ピーマンの苗は徒長しやすいので、風通しの良い場所で育てたり、ときどき鉢の向きを変えたりして、日光にまんべんなく当たるように工夫しましょう。
- ピーマンの種まき時期: 4月~5月頃
- 発芽適温: 25~30℃
- 間引き: 双葉が開いたら、元気な苗を1本残す
- ポット上げ: 本葉が2~3枚になったら、9cmポットに植え替える
苗作りの詳しい方法や、土作りについては「大根 土作り」の記事も参考にしてみてください。
ピーマン 育て: 種まきから苗作り
2. ピーマン 育て: 畑の準備と植え付け
ピーマンにピッタリの土作り
ピーマンは、水はけがよくて栄養たっぷりの土が大好き! 植え付けの2週間前までに、畑に石灰や堆肥を混ぜてよく耕しておきましょう。石灰は、酸性になりがちな土を中和して、ピーマンが元気に育つ環境を作ってくれます。堆肥は、土に栄養を与えて、ふかふかの土にしてくれます。土作りは、ピーマン 育ての大切な第一歩です。
ピーマンの植え付け: 時期とポイント
ピーマンの苗を畑に植え付けるのは、5月に入ってからがおすすめです。霜が降りる心配がなくなってから植え付けましょう。苗を植えるときは、株間を50cmくらいあけて、深めに植えます。深めに植えることで、根っこがしっかりと張って、丈夫なピーマンが育ちます。植え付け後は、たっぷりと水やりをして、苗を落ち着かせましょう。支柱を立てて、風で倒れないようにすることも忘れずに!
連作障害を防ぐために、ナス科の野菜(ナス、トマト、ピーマンなど)を続けて同じ場所で育てないようにしましょう。ナス科の野菜を育てた場所には、2~3年は他の野菜を育てるのがおすすめです。連作障害についてもっと知りたい人は、「イチゴ 疑問 栽培」の記事もチェックしてみてね。
野菜の種類 | 連作障害の症状 |
|---|---|
ナス科 | 生育不良、病害虫の発生 |
アブラナ科 | 根こぶ病 |
ウリ科 | つる割れ病 |
ピーマン 育て: 畑の準備と植え付け
3. ピーマン 育て: 日々のお世話とコツ
ピーマンの水分補給: 水やりのタイミングと方法
ピーマンは、お水をたくさん飲むのが大好き!特に夏は、土が乾きやすいので、朝と夕方の2回、たっぷりと水やりをしましょう。ピーマンの葉っぱがしおれていたら、それは「のどが渇いたよ~」というサインです。すぐに水やりをしてあげましょう。水やりをするときは、株元に優しく水をかけましょう。葉っぱや花に水がかかると、病気になってしまうことがあるので注意が必要です。
ピーマンの栄養補給: 追肥の時期と種類
ピーマンは、栄養をたくさん必要とする野菜です。植え付けから2~3週間後から、2週間に1回程度、追肥をして栄養補給をしましょう。追肥には、野菜用の肥料や、油かす、鶏糞などを使うことができます。肥料は、株元から少し離れたところにまいて、土と軽く混ぜ合わせましょう。肥料を直接根っこにかけると、根っこが傷んでしまうことがあるので注意が必要です。肥料の種類や使い方については、「農業 肥料」の記事も参考にしてみてください。
- 化成肥料
- 有機質肥料
- 液体肥料
ピーマンの整枝: わき芽かきと3本仕立て
ピーマンは、枝がたくさん出てくると、風通しが悪くなって病気になりやすくなります。そこで、わき芽をこまめに取り除いて、風通しを良くしましょう。わき芽は、葉っぱと茎の間から出てくる小さな芽のことです。わき芽かきは、手で簡単にできます。ピーマンは、主枝と側枝2本の、合計3本仕立てで育てるのが一般的です。3本仕立てにすることで、栄養が分散せずに、大きなピーマンがたくさん収穫できます。3本仕立ての方法は、「ピーマン 栽培」の記事も参考にしてみてください。
ピーマンの支柱立て: 倒伏防止と誘引
ピーマンは、茎が細くて折れやすいので、支柱を立ててあげましょう。支柱は、ピーマンの苗と同じくらいの高さのものを選びます。支柱を立てることで、風で倒れたり、実の重さで枝が折れたりするのを防ぐことができます。ピーマンの茎が伸びてきたら、麻ひもやビニールタイなどを使って、支柱に誘引してあげましょう。誘引することで、ピーマンがまっすぐに育ち、風通しも良くなります。誘引の方法は、「トマト 植え付け」の記事も参考にしてみてください。
ピーマン 育て: 日々のお世話とコツ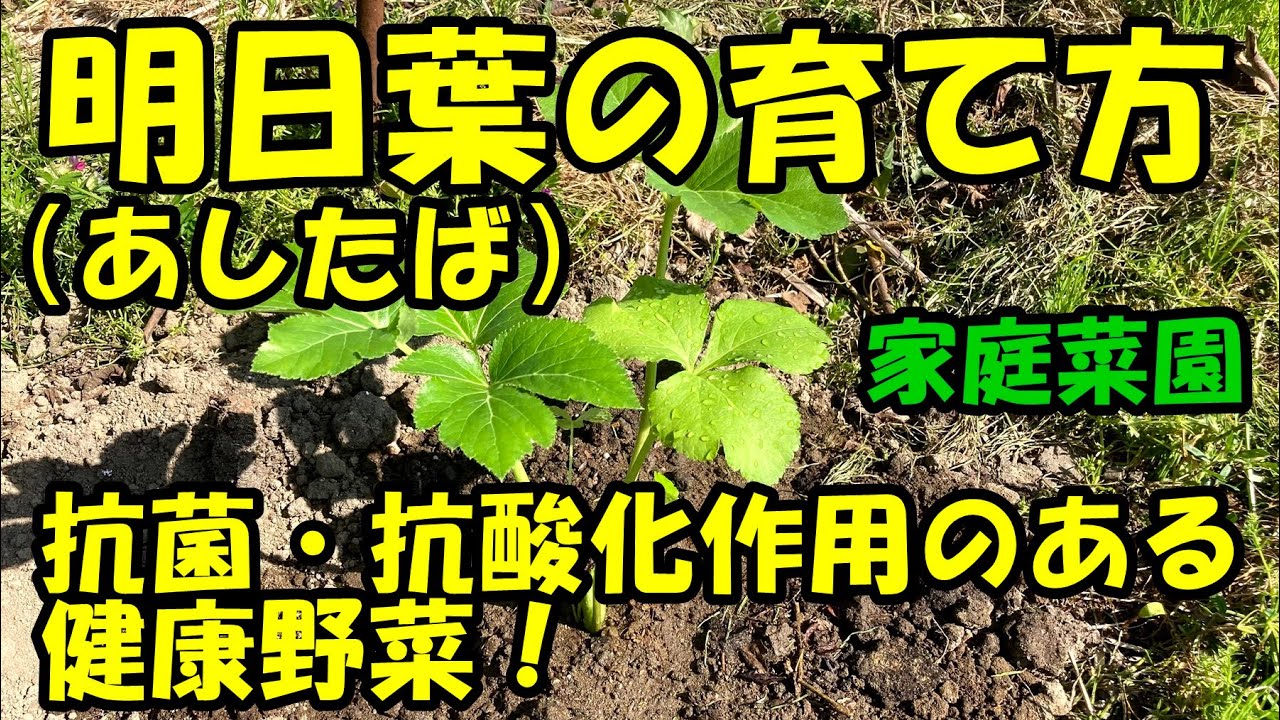
4. ピーマン 育て: 収穫と楽しみ方
ピーマンの実が大きく育って、ツヤツヤと輝いていたら、収穫のサイン!ピーマンは、緑色の未熟果を収穫するのが一般的ですが、完熟させて赤や黄色など、カラフルなピーマンを収穫することもできます。完熟ピーマンは、甘みが強くて美味しいですよ。収穫するときは、ハサミを使って、ヘタの少し上を切ります。手で収穫すると、枝が折れてしまうことがあるので注意が必要です。
収穫したピーマンは、そのまま生で食べても美味しいですし、炒め物や煮物、天ぷらなど、いろいろな料理に使えます。ピーマンが苦手な人は、肉詰めやピーマンの味噌炒めなど、ピーマンの苦みが抑えられる料理がおすすめです。ピーマンを使ったレシピについては、「きゅうり 栽培」の記事も参考にしてみてください。
ピーマン 育て: 収穫と楽しみ方
Final Thought
ピーマンは、ポイントを押さえれば初心者でも簡単に育てることができる野菜です。毎日の観察を忘れずに、愛情込めて育てれば、きっとたくさんの美味しいピーマンを収穫できるでしょう。ぜひ、家庭菜園でピーマン栽培に挑戦して、新鮮なピーマンを味わってみてください!